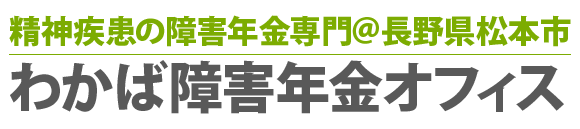障害基礎年金となります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
知的障害は生まれつきの障害という扱いですので、会社員や公務員が加入する厚生年金の対象とはなりません。
したがって、障害基礎年金のみを受給します。
795,000円です。(令和5年度)
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。
振込月の15日に、2か月分が後払いで振り込まれます。
※15日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。
(例)8月15日に6月分と7月分が振り込まれ、金額は約130,000円です。
知的障害で申請する場合の初診日は「生まれた日」となります。
そのため、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)は必要ありません。
①診断書
医師が作成します。日常生活における不自由さや受けている支援の状況が正しく医師に伝わっていないと、実態に沿わない診断書が作成されてしまいます。
②病歴・就労状況等申立書
ご本人やご家族等の支援者が作成します。
日常生活における不自由さや受けている支援の状況を、丁寧に記載する必要があります。
「大まかに書いておけば審査する人はわかってくれるだろう」という考えは非常に危険です。
書類審査のみで年金受け取りの可否が判定されますので、主張すべきことはきちんと訴えておかなければなりません。
いつから申請できるの?
20歳に到達した日からです。
(例)誕生日が平成13年8月20日であれば20歳に到達した日は令和3年8月19日、誕生日が平成13年8月1日であれば20歳に到達した日は令和3年7月31日となります。
「20歳に到達した日」とは、20歳の誕生日前日を指します。
いつから受け取れるの?
20歳に到達した日の翌月分からです。
(例)誕生日が平成13年8月20日であれば9月分から、誕生日が平成13年8月1日であれば、8月分からとなります。
受け取りまでのながれ
20歳の4か月前~3か月前
★住所地のある役所へ出向き、診断書、病歴・就労状況等申立書などの申請書類を受け取る
★医療機関に受診の予約を入れる
20歳の3か月前~2か月前
★医療機関を受診、診断書の作成を依頼する
★病歴・就労状況等申立書を作成する
20歳到達日後すみやかに
★役所へ書類一式を提出する
年金機構の審査
★審査には3か月ほどかかる
★受給が決定した場合は、年金証書が届く
年金証書到着後すみやかに
★国民年金保険料の法定免除申請書を役所に提出する
企業等に勤務(正社員・障害者雇用問わず)して厚生年金に加入している場合は、給料から厚生年金保険料が控除されているので、免除申請をする必要はありません。
年金証書到着から約50日後
★初回の年金が口座に振り込まれる
※3~4か月分まとめて振り込まれたり、奇数月に振り込まれる場合もある
療育手帳がなくても申請可能
幼少期に医療機関の受診がないと、療育手帳を所持していないケースもあります。
障害年金を申請するための条件として、「療育手帳を持っていること」という規定はありませんので申請は可能です。
特別支援学校や特別支援学級の在籍経験がなくても申請可能
療育手帳の所持と同様に、申請の条件となっていませんので申請できます。
医療機関を探す
知的障害の障害年金を申請するための診断書を作成してくれる医療機関を探します。
心理士が在籍していて、知能検査をしてくれる医療機関が望ましいでしょう。
病歴・就労状況等申立書の作成が大変
生まれた時からの日常生活の実態を記入しなければなりません。
申請が遅れれば遅れるほど、過去の記憶が曖昧となり困難な作業となります。
親御さんがご健在であれば幼少期の様子を聞いてみるのも良いですし、通知表を保管していれば作成の参考資料となります。
(Q)療育手帳があれば受け取れますか?
受け取れないケースもあります。療育手帳の交付基準と障害年金の審査基準はまったく違うためです。
(Q)特別支援学校や特別支援学級の在籍経験があれば受け取れますか?
この理由のみでは受け取れません。
(Q)生涯ずっと受け取れますか?
知的障害は生まれつきの障害ではありますが、審査では、ほとんどのケースで有期認定となります。
有期認定とは、1年から5年の間隔で年金の受け取りを認めるというものです。
したがって、所定の年数が経過した時点で、引き続き年金が受け取れる障害状態なのかを日本年金機構が確認する手続きがあります。
そのため、1回認められたとしても、永久に受け取れることが決まったわけではありません。
病状に変化がないにもかかわらず、年金が打ち切りとなるケースもあります。
(Q)医療機関には通院していません。どうすれば良いですか?
必ず医師の診断書が必要となるため、医療機関を受診する必要があります。
初診時に、「知的障害で障害年金の申請をしたい。診断書の作成をお願いできますか」と単刀直入に医師にお聞きするのが良いでしょう。
医師によっては難色を示す場合もありますので、障害年金の申請に理解のある医師を探すことがポイントです。
(Q)特別児童扶養手当用の診断書で申請しても良いですか?
国からの事務通達で、直近の特別児童扶養手当用の診断書で障害年金の申請が可能とされていますが、正直オススメしません。
なぜなら、自動的に障害年金の支給を決定するとは言っていないからです。
特別児童扶養手当申請用の診断書は、障害年金申請用の診断書と比較すると内容が非常に簡素化されています。
したがって、日常生活の実態がきちんと伝えられず正当な判定を受けられない恐れがあることから、当初から障害年金申請用の診断書を使用したほうが良いでしょう。
(Q)就労支援施設や障害者雇用で働いていると受け取れませんか?
そのようなことはありません。ただし、職場で受けている配慮や援助の内容をきちんと診断書や病歴・就労状況等申立書で伝えることができていないと、障害状態が軽度であると判断されてしまい受け取れないことも多いです。
(Q)1人暮らしでも受け取れますか?
受け取れない可能性が高くなります。日本年金機構は、1人暮らしをしているかどうかを重視する傾向にあると思われるからです。
つまり、「1人暮らしできるなら日常生活には支障がないよね」という理屈です。
どのような理由で1人暮らしをしているかが重要です。
(Q)厚生年金加入中に医療機関を受診して知的障害と診断されたら、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れますか?
できません。あくまでも申請日は「生まれた日」となるからです。
(Q)20歳で申請するのを忘れてしまい23歳で申請します。20歳のときに遡って申請できますか?
20歳時点(20歳誕生日の前後3か月以内)で医療機関の受診があればさかのぼって申請できます。
受診がない場合は申請できないため、未来に向けての申請のみになります。
したがって、20歳誕生日の前後3か月以内のどこかの時点で受診しておくことが必要です。
また、20歳から5年以上経過してからさかのぼって申請した場合は、申請時点から5年を過ぎてしまった年金は時効により受け取ることができません。
乳幼児健診でも発達の遅れなどを指摘されたこともなく、医療機関の受診経験もありませんでした。
しかし、幼少期の頃から勉強が苦手で、他のクラスメイトとも行動のテンポが合わないことが多くありました。
小中学校とも普通学級で過ごし高校を卒業し、推薦で短大に進学し卒業しました
40代になってから知的障害と診断され、療育手帳は所持していません。
年金事務所に障害年金の申請ができるか問い合わせたところ、可能との案内がありました。
しかしながら、主治医に診断書の作成を申し出たところ「療育手帳を持っていない」「特別支援学校や特別支援学級に在籍したことがない」「短大を卒業している」という理由で診断書の作成はできないと断られました。
主治医の交代を申し出ましたが、希望が叶いませんでした。
別の医療機関に相談したところ診断書の作成が可能との回答を得たため、紹介状を書いてもらい転院しました。
1回の受診で診断書を作成してもらえました。審査の結果、2級の年金受け取りが決定しました。
医師の言葉をそのまま信用していたら、受け取りには結びつかないケースでした。
申請する権利すら奪われかねないところでした。医師は病気の治療を行う専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。医師の言葉を鵜呑みにせず、少しでも疑問や不安を感じたら当オフィスにご相談ください。
幼少期からの病歴や日常生活の実態がほぼ一緒、勤務先が異なっていましたが申請時には就労しており勤務体系や賃金の額もほぼ一緒、知能指数や病歴・就労状況等申立書の内容もほとんど一緒でした。
しかしながら1人は有期3年で認定され、もう1人は有期1年で認定されました。
なぜ結果が異なるのか意味不明です。
考えられる理由としては、障害年金の審査は障害年金センター(東京都)で全国の案件を一括集中管理で行っています。
審査する医師(認定医)も大人数が委嘱されているため、別々の認定医が担当したものと思われます。
もしどちらかが受け取れないとの審査結果だったとしたら、不服申し立て(審査請求)をすれば覆る可能性が高いケースだと思われます。今回のように、有期年数が片方に比べて短いのは納得がいかないという理由では、審査請求することが認められていません。有期年数を何年で設定するかは、日本年金機構の裁量に委ねられているため不服の申し立てができません。診断書や病歴・就労状況等申立書の内容がほぼ同一であるため、なぜ異なる判断に至ったのか釈然としないケースです。
小中学校では普通学級で過ごしたものの、読み書きが満足にできず勉強が苦手でした。
現場作業や農業など日雇いの仕事を20年ほど転々としていました。
1人暮らしでしたが、50代になってから知能検査を受け障害年金の申請をしました。
ところが、受け取れないとの結果になりました。
障害年金の申請をしても受け取れないと判定された場合は、日本年金機構から申請者あてに「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ」(不支給決定通知書)が送付されます。
その決定通知書には、なぜ支給しないと判断したのかの理由が示されています。
このケースでは、「在宅で生活しており同居者はいない」と記載されていました。
この他にも理由があり支給しないと判断されたものですが、1人暮らしをしているという事実が影響を与えていることは明らかです。
なぜ1人暮らしをするに至ったかを診断書や病歴・就労状況等申立書に記入する必要があります。例えば、「両親は他界しておりやむなく1人暮らしをしている」「家族と同居すると病状が悪化するため、やむなく別居している」「少しでも自立した生活を営めるよう近隣の両親を頼りながらあえて1人暮らしをしている」などと、理由を記載しなければなりません。日常生活が成り立たない状態であっても、診断書や病歴・就労状況等申立書からその理由を読み取ることができないと、審査する側には事情が伝わらないからです。
ご自身やご家族で申請して後悔したくないと思われましたら、知的障害に詳しい当オフィスにご相談ください。
0263-88-5404